近年、インディーゲーム界隈で注目を集めている作品のひとつが「That’s not my neighbor」です。
本作は、1950年代のアパートを舞台に、偽物の住人「ドッペルゲンガー」を見抜くというユニークな設定が話題となっています。
緊張感のあるゲーム性と独特の世界観が高く評価され、SteamやYouTubeなどでもプレイ動画が急増中です。
ゲームの特徴:「ドッペルゲンガーを見抜く」新感覚ホラーアドベンチャー

ただのホラーゲームではなく、観察力と論理的思考が問われる推理アドベンチャー。
それが「That’s not my neighbor」の真骨頂です。
1950年代アパートが舞台のレトロな雰囲気
本作の舞台は1955年、架空のアパートメント。
プレイヤーは新人管理人として、住人の入居チェックを任されます。
グラフィックはモノクロ調やくすんだ色彩で統一されており、1950年代の社会背景や生活感を忠実に再現しています。
家具や服装、書類のデザインにもこだわりがあり、レトロ感を演出しつつも不気味さを引き立てています。
時代考証に基づいたアートワークが、没入感を高める重要な要素となっています。
ドッペルゲンガーとは?見分け方のコツ
ゲームの核心は「ドッペルゲンガーの判別」です。
本物の住人と偽物を見分けるために、書類や顔写真、話し方の違和感など多角的に情報を精査します。
ドッペルゲンガーは細かい特徴を偽っており、例えばIDカードの写真が微妙に違う、発言に矛盾があるなどの違和感を見つける必要があります。
プレイヤーは観察力を駆使し、疑わしい人物を通報する判断力が求められます。
これは「Papers, Please」などと同様の書類照合システムを取り入れており、緊張感のあるプレイ体験を生み出しています。
管理人としての仕事とミスのリスク
プレイヤーの役割は、住人の審査業務を遂行する“管理人”です。
しかし、この業務には重大な責任とリスクが伴います。
誤って本物の住人を通報してしまうと、評価が下がりゲーム進行に影響が出ることがあります。
逆にドッペルゲンガーを見逃すと、住人が襲われるなどのバッドエンドに直結します。
そのため、迅速かつ正確な判断が求められます。
ミスの許されない環境下での作業は、プレイヤーに常に緊張感とプレッシャーを与え、スリル満点のゲーム体験を提供してくれます。
モード紹介:カスタムやナイトメアなど多彩なプレイスタイル
本作は複数のプレイモードを搭載しており、それぞれ異なる楽しみ方が可能です。
初心者から熟練者まで幅広く対応しています。
キャンペーンモードとエンディング分岐
キャンペーンモードでは5日間のシナリオを通して、入居審査の業務をこなしていきます。
毎日の難易度が徐々に上がる構成となっており、ストーリー性がある点が特徴です。
プレイヤーの判断によってストーリー分岐が発生し、複数のエンディングが用意されています。
正確な判断を積み重ねることでベストエンディングにたどり着けますが、見逃しや誤判定によってバッドエンドへ向かうこともあります。
判断力と選択が物語の結末を左右する、リプレイ性の高いモードです。
スコア重視のアーケードモード
アーケードモードはスコアの更新を目的としたタイムアタック形式のモードです。
制限時間内により多くの入居者を正確に審査し、得点を競う仕組みになっています。
審査スピードや精度によってスコアが変動するため、短時間で集中力を求められます。
ランキング機能やリプレイ性も高く、競技的な要素を楽しみたいユーザーに最適です。
また、アーケードモードはキャラクターや演出がテンポよく進行するため、繰り返しプレイしても飽きにくい構成となっています。
難易度最強「ナイトメアモード」とは
ナイトメアモードは最高難易度に設定された上級者向けの挑戦モードです。
通常のドッペルゲンガーに加えて特殊個体やフェイク書類が多数登場します。
制限時間も厳しく設定されており、少しの判断ミスが致命的な結果につながります。
注意力・反応力・記憶力のすべてを要求される構成で、非常に緊張感のあるプレイが展開されます。
誤判定による即終了など厳しいルールがある一方、攻略に成功すれば実績解除などのご褒美も用意されています。
住人カスタマイズで自作ドッペルゲンガーも可能?
本作には「カスタムモード」と呼ばれるモードが存在し、ユーザーが住人の外見やプロフィールを自由に設定できます。
これにより自作ドッペルゲンガーを作成することも可能です。
設定項目は顔のパーツ、服装、音声、身分証情報など多岐にわたります。
自分自身や友人に似せた住人を作成し、ゲームに登場させることもできます。
また、作成した住人に対してAIが自動でドッペルゲンガー化のロジックを適用し、独自のシナリオを構築することもできます。
ユーザーによる創造性が発揮される自由度の高いモードです。
「質問してくる人」チェスターの正体とクイズの答えまとめ
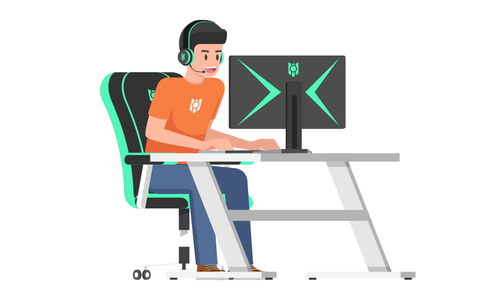
キャンペーンモード中に現れるチェスターは、本作の世界観とゲーム性をより深める存在です。
彼の登場には特別な意味があります。
チェスターって誰?ゲーム内での役割
チェスターはD.D.D.(ドッペルゲンガー検出部)から派遣された監査官で、プレイヤーの業務遂行力を試す目的でクイズを出題してきます。
彼は1日1問ずつ、合計5問の問題をランダムに出題します。
問題の内容はSF文学や数学、論理パズルなど多岐にわたり、専門知識が求められる設問も含まれます。
正解してもゲームの進行には直接影響しませんが、全問正解で取得できるSteam実績が存在するため、やり込み要素のひとつとなっています。
クイズ内容と全5問の答え一覧(Steam実績あり)
チェスターの出題するクイズには固定パターンがあり、バージョン2.0.4時点で確認されているのは以下の5問です。
すべて正解すると「クラスで一番優れた」という実績が解除されます。
- 「銀河ヒッチハイク・ガイド」が出版された年 → 答え:1979年
- 重要なメルセンヌ素数の順列数 → 答え:302400
- アルファベットの線数を使った暗号計算 → 答え:428653855
- 幸せな回文数のべき集合の要素数 → 答え:536870912
- 9桁自然数のランダム正答確率 → 答え:900000000
これらの問題は、いずれも一般常識では解けない高度な内容で、プレイヤーに知的な刺激を与えています。
クイズを無視しても大丈夫?注意点とメリット
チェスターのクイズに答えなかった場合でも、ゲームの進行にペナルティはありません。
クイズはあくまで挑戦要素であり、回答をスキップしてもキャンペーンは続行可能です。
ただし、全問正解での実績獲得はできなくなり、再挑戦するには最初からやり直す必要があります。
また、同じ問題が繰り返し出題されるため、正解を覚えておけば次回以降の達成が容易になります。
難問であるがゆえに無視したくなる場面もありますが、やり込み派や実績収集が好きなユーザーにとっては挑戦する価値があるコンテンツです。
まとめ
「That’s not my neighbor」はプレイモードも多彩で、ストーリー重視のキャンペーンから、ハイスコアを狙うアーケード、極限の判断力が問われるナイトメアモードまで幅広く用意されています。
また、チェスターによる知的クイズや住人カスタマイズなど、奥深い仕掛けが多数存在し、長く遊べる設計となっています。
気になる方はまずSteam版から体験してみてはいかがでしょうか。


