2025年10月14日をもってWindows 10のサポートが終了します。
しかし、すぐにパソコンを買い替えたり、Windows 11へ移行できない方も多いはずです。
そんなときに活用できるのが、Microsoftが提供するESU(拡張セキュリティ更新)です。
この記事では、サポート終了後に想定されるリスクやESUの役割、実際にESUを無料で利用するための条件や手順を、専門用語も交えつつわかりやすく解説します。
サポート切れOSを安全に使いたい方や、セキュリティ対策に悩む方はぜひ最後までご覧ください。
Windows 10サポート終了で何が起こる?リスクと今後

2025年10月14日にWindows 10の公式サポートが終了します。
サポート切れとなることで、どのような危険があるのか気になる方も多いでしょう。
ここでは主な影響やリスクについて解説していきます。
Windows 10サポート終了日・影響まとめ
Windows 10のサポート終了日は2025年10月14日です。
この日を境にセキュリティパッチや機能更新が一切配信されなくなります。
サポートが切れると、OSの脆弱性がそのまま放置されるため、利用を続ける場合は重大なリスクを常に抱えることになります。
サポート終了後の運用には注意が必要です。
サポート切れOS利用時のセキュリティリスクとは?
サポートが終了したOSは、マルウェア感染やゼロデイ攻撃、不正アクセスの標的になりやすくなります。
サイバー犯罪者は未修正の脆弱性を狙うため、インターネットに接続したままの運用は非常に危険です。
また、脆弱性管理の観点からも、セキュリティベンダーや専門家はサポート切れOSの利用を強く非推奨としています。
ウイルス感染・不正アクセス・個人情報漏洩の危険性
サポートが切れることでウイルスやランサムウェアに感染する確率が高まります。
特にネットバンキングやECサイトを利用する場合、個人情報やパスワードの漏洩リスクが急増します。
不正アクセスによる遠隔操作や情報搾取など、実害が発生するケースも多く、実際の被害例も報告されています。
OSのサポート期間を意識した運用が必須です。
ESU(拡張セキュリティ更新)とは?延命措置の全体像
サポートが切れても、すぐにWindows 11へ移行できない人のために、MicrosoftはESU(拡張セキュリティ更新)という延命策を用意しています。
ここではESUの仕組みや利用の意義について説明します。
ESUの概要と役割
ESU(Extended Security Updates)は、Windows 10のサポート終了後もセキュリティ更新プログラムだけを一定期間受け取れる延長サービスです。
本来は企業向け有料サービスですが、特定条件を満たせば個人でも1年間無料で利用できます。
ウイルス対策や脆弱性対応といった基本的なセキュリティ維持のための手段です。
ESUは個人利用も可能?企業向けとの違い
ESUはもともと法人向けに年間契約で提供されていました。
しかし、2025年からは個人でも特定の条件をクリアすれば無料で利用できます。
企業向けと個人向けでは提供方法やライセンス管理に違いがあり、個人の場合はMicrosoftアカウントを利用した簡単な登録が主流です。
個人ユーザーにとっても現実的な選択肢となっています。
1年間の無料提供と適用期間(2025年10月15日~2026年10月13日)
ESUの無料提供期間は2025年10月15日から2026年10月13日までの1年間です。
この期間中は、Windows 10の最新バージョン(22H2)を対象に、セキュリティパッチのみ配信されます。
無償延長は“移行準備の猶予”と位置付けられているため、無料期間中に次の環境への乗り換え計画を進めておくことが大切です。
ESUを無料で利用するための条件・注意点
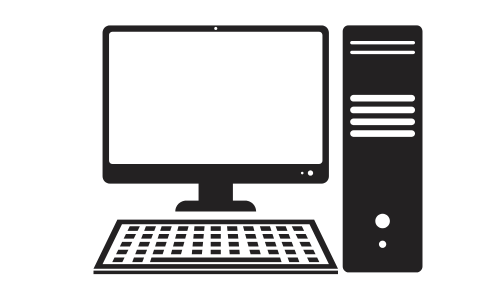
ESUを無料で利用するには、いくつかの条件や注意点をクリアする必要があります。
ここでは対象バージョンの確認や必要なアカウント設定について詳しく説明します。
Windows 10のバージョン・環境要件チェック方法
ESUの無料対象となるのは、Windows 10の最新バージョン「22H2」を利用している場合だけです。
今のパソコンがこの要件を満たしているか、事前に確認しましょう。
合わせて最新の累積更新プログラムも適用しておく必要があります。
Windows 10「22H2」バージョン確認手順
まずはWindowsの「設定」から「バージョン情報」を開き、バージョン番号が「22H2」と表示されているかをチェックします。
もし異なる場合は、Windows Updateを実行し、システムを最新版へ更新します。
最新バージョンの維持は、セキュリティ上も重要なポイントです。
最新累積更新プログラム(KB5062649以降)適用の方法
累積更新プログラムは、Windows Updateを通じて適用できます。
対象となる「KB5062649」以降のアップデートがインストールされているか、更新履歴で確認してください。
未適用の場合は、手動でアップデートを行いましょう。
最新状態を保つことがESUの利用条件を満たすカギとなります。
必要なMicrosoftアカウントの設定
ESUを無料で使うにはMicrosoftアカウントでサインインし、設定同期が有効になっていることが必須です。
ローカルアカウントからの切り替え方法や、同期に関するプライバシーの注意点も押さえておきましょう。
ローカルアカウントからの切り替え方法
ローカルアカウントを使っている場合は、「設定」→「アカウント」からMicrosoftアカウントへの切り替えができます。
切り替え手続きは数分で完了し、途中でデータが消えることはありません。
サインイン後は必ず同期設定も有効にしておきます。
プライバシーとアカウント同期の注意点
Microsoftアカウントで同期を有効にすると、一部設定やデータがクラウドに保存されます。
プライバシー保護の観点から、同期内容やOneDriveの設定も確認しておくと安心です。
ESUのための同期は一時的な措置でも構いませんが、個人情報管理の意識が大切になります。
ESU無料登録手順とやり方
ESUを無料で利用するためには、Microsoftが指定するいずれかの方法で登録を行う必要があります。
それぞれの手順を分かりやすく解説していきます。
方法1:Windows バックアップを使ったクラウド同期
Windows バックアップを利用してクラウド同期を行うことで、ESUの無料提供を受けられる仕組みです。
アカウント同期が未設定の方も、流れを確認してから進めると安心です。
同期設定の手順
「設定」から「Windows バックアップ」を開きます。
画面案内に従ってMicrosoftアカウントでサインインし、同期を有効にします。
同期をオンにすることで、自動的にクラウドにデータが保存されるようになります。
ここまで終えたら、後日「ESU登録」の案内がWindows Update画面に表示される場合があります。
設定項目の選び方(アプリ・資格情報・設定)
同期設定では、どの項目を同期するか選択できます。
アプリの設定やWi-Fiパスワード、個人用設定などを同期対象に含めることで、クラウド同期の効果を最大限に活かせます。
ただし、プライバシーを気にする場合は同期する内容を事前に見直すと良いでしょう。
必要最低限の項目だけ選ぶ方法も可能です。
方法2:Microsoft Rewardsポイントを使う方法
ESUの無料利用には、Microsoft Rewardsポイントを使う方法も用意されています。
ポイントが1,000pt以上ある方は、こちらも簡単に手続きできます。
ポイントの貯め方と確認方法
Microsoft Rewardsポイントは、Bing検索やMicrosoft Storeの利用、タスク達成などで自動的に貯まります。
現在のポイント数は、MicrosoftアカウントのRewardsページで確認できます。
日常的にサービスを利用していれば、気づかないうちに必要なポイントが貯まっていることも多いです。
交換手順と必要ポイント数(1,000pt)
ポイントが1,000pt以上ある場合は、Rewardsページから「ESU無償延長」を選択して手続きします。
案内に従ってポイントを交換し、Windows Update画面で「ESU登録」を行います。
登録後、必要なアップデートが自動的に適用されます。
複雑な操作は不要で、誰でも簡単に完了できます。
ESU登録後に注意すべきポイント
ESU登録が完了した後も、いくつか気をつけたいポイントがあります。
ここでは、よくある疑問やトラブル回避策についてまとめます。
クラウド同期後にローカルアカウントへ戻す手順
登録時にMicrosoftアカウントを使った場合でも、後からローカルアカウントへ戻すことは可能です。
「設定」→「アカウント」からアカウントの種類を切り替えます。
ただし、Microsoftはローカルアカウント利用時のESU継続を保証していません。
アップデートが届かない場合は再度サインインし直すことも検討しましょう。
Windows Updateが正常に動作しているか確認方法
ESU登録後はWindows Updateが正常に機能しているか定期的に確認することが大切です。
「設定」→「更新とセキュリティ」→「Windows Update」から更新の状況を確認できます。
万一アップデートが適用されない場合は、Microsoftアカウントへの再ログインやネットワーク環境の見直しも行います。
ESU無料延長後の選択肢・移行パターン

ESUを使って1年の猶予を得られますが、その後の進路を早めに考えることが大切です。
ここでは移行方法の選択肢や注意点について紹介します。
Windows 11へのアップグレード条件とおすすめ機種
Windows 11へのアップグレードには、TPM 2.0や第8世代以降のCPUなどハードウェア要件があります。
現在のパソコンが要件を満たしているかは「PC正常性チェック」アプリで簡単に確認可能です。
推奨される機種は、セキュリティ機能が強化されたモデルやSSD搭載機種です。
ハードウェアのスペックを確認し、無理なく移行できる環境を整えましょう。
パソコン買い替え時のチェックポイント
新しいパソコンを購入する際は、OSのサポート期間やスペックだけでなく、保証内容やメーカーのサポート体制も確認しましょう。
データ移行や旧機種の下取り、不要になったパソコンの安全な処分方法もあわせて検討しておくと安心です。
最新機種の選び方やコストパフォーマンスも重要な比較ポイントです。
Linux移行のメリット・注意点
Webブラウジングやオフィス作業が中心であれば、Linuxへの移行も有効な選択肢です。
Linuxは無償でセキュリティリスクが少ない点が魅力です。
一方で、Windows専用アプリが使えない場合があるため、利用用途や互換性を事前に確認しておくことが必要です。
初めてLinuxを使う場合はサポートが充実したディストリビューションを選ぶのが安心です。
オフライン端末としての利用方法とリスク
サポート切れのWindows 10をネットワークに接続せず、オフライン専用端末として活用する方法もあります。
オフライン運用により外部からの不正アクセスやウイルス感染リスクは大幅に下がります。
ただし、USBメモリなどを経由したマルウェア感染やデータ持ち出しの危険性は残るため、外部媒体の利用管理や物理的なセキュリティ対策も欠かせません。
よくある質問(FAQ)・困ったときの対策
ESUやサポート終了に関して、よくある質問やトラブル時の対処法をまとめました。
今後の安全な運用に役立ててください。
「ESU登録できない場合は?」
登録できない場合は、Windows 10のバージョンや累積更新プログラム、Microsoftアカウントの状態を再確認してください。
ネットワーク環境が不安定な場合や一時的なサーバートラブルも考えられます。
手順通り進めても解決しない場合は、公式サポートへの問い合わせや再起動を試してみてください。
「セキュリティ以外のサポートはどうなる?」
ESUによって提供されるのは、あくまでセキュリティ更新プログラムのみです。
新しい機能追加やパフォーマンス改善、バグ修正などは対象外となります。
業務アプリや周辺機器のトラブル対応も終了するため、サポート切れOSを利用する際は自己責任が伴います。
長期運用には十分な注意が必要です。
「古いパソコンはどこまで使える?」
ハードウェアが十分に動作する限り古いパソコンも使い続けることは可能です。
ただし、サポート切れOSでは脆弱性のリスクが高まるため、重要なデータや個人情報の扱いには特に注意が必要です。
性能面や安全面で不安がある場合は、早めの買い替えや他OSへの移行も検討しましょう。
サポート終了後も安全に使うための追加対策
サポートが切れても使い続ける場合は、セキュリティソフトの導入やファイアウォールの強化、定期的なバックアップの実施が不可欠です。
さらに、不要なネットワーク接続の制限やアプリの自動起動設定の見直しも重要です。
常に最新情報をチェックし、危機管理意識を高めた運用を心掛けましょう。
まとめ
Windows 10のサポート終了は大きな転換点です。
ESUの無料延長をうまく活用すれば、1年の猶予期間を確保できます。
この期間中に移行計画を立て、ハードウェアやOS環境の見直しを進めていきましょう。
リスクを正しく理解し、次のステップに備えることで、これからも安全で快適なパソコン利用が可能になります。


